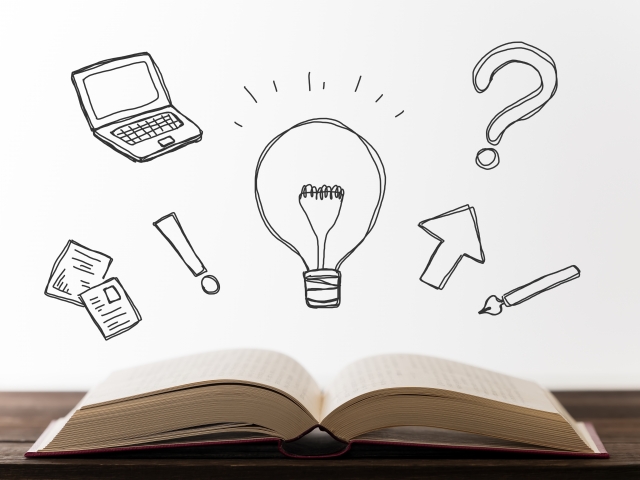SNS上には、目を奪う成功事例や劇的なビフォーアフターが溢れています。
しかし、現実の仕事はその多くが地道な積み重ね。日々の努力や挑戦が可視化されにくいからこそ、「この会社は本当に動いているのか?」という疑念すら生まれかねません。
そこで、“プロセスを切り取って見せる”発信です。結果ではなく進行中の姿。完成形ではなく途中経過。こうした「動き続けている証拠」が、じわじわと信頼につながっていきます。

「#今日の一歩」という企業発信の新しい単位
1日の進捗や小さな気づきを15秒程度の動画にまとめて、SNSに「#今日の一歩」として毎日投稿するという取り組み。
たとえば「新しい機材の初期設定が完了」「営業資料の一部をアップデート」など、成果とは言えないが、たしかに進んでいる様子を動画で見せるのです。
特徴は以下の3つ
| 項目 | 内容 |
| 動画時間 | 10~15秒程度 |
| 投稿内容 | 当日の進捗、小さな改善、学びなど |
| 表現スタイル | テロップ+BGM(語りなし) |
続けるほどに、「この会社、ちゃんと動いてるな」という“蓄積”が可視化されていきます。
なぜ小さな一歩が信頼につながるのか?
人は「自分ごとに引き寄せられる」傾向があります。
大きな成果よりも、「わかる、その地味さ」「うちの会社もこういう日あるよな」と共感できる瞬間のほうが、記憶に残るのです。
また、動画という形を取ることで、「実際にその日、その場所で、誰かが動いていた」という“確かさ”も伝わります。文章では曖昧になりがちな現場感が、動画なら一目で伝わるのです。
続けるための工夫は「ルール化」と「軽量設計」
毎日投稿するには継続可能な設計が必要です。そこで、以下のようなルールを決めればいいでしょう。
- 撮影・編集は1人の担当者が15分以内で完結
- 毎週月曜に5日分の素材を撮りためる
- 編集テンプレートを用意し、構成を固定化
これにより、負担を最小限にしながら“続けること”を最優先に据えた運用が可能になりました。
成果は追わない。でも信頼は残る
このSNS動画実験には「いいね数を追わない」なくていいでしょう。
KPIは「社外の誰かが、その会社の“動き”を知ること」。
結果的に、「SNS経由での採用応募」「取引先からの共感メッセージ」など、副次的な反応が少しずつ生まれるでしょう。
つまり、成果は後からついてくる。
最初から成果を求めるのではなく、「動いている会社」という印象を積み重ねることが、真のブランディングにつながるのです。
いま求められているのは、劇的な成果ではなく、“動いている証拠”です。
15秒の「#今日の一歩」動画という試みは、小さな進捗でも発信を続けることで、企業への信頼を少しずつ積み上げていきます。
SNSを使った企業動画の形も、「見栄え」ではなく「積み重ね」にシフトしています。派手ではない。でも、見る人にはしっかり伝わる。そんな地道な実験こそ、いまの時代に最もフィットした動画戦略かもしれません。