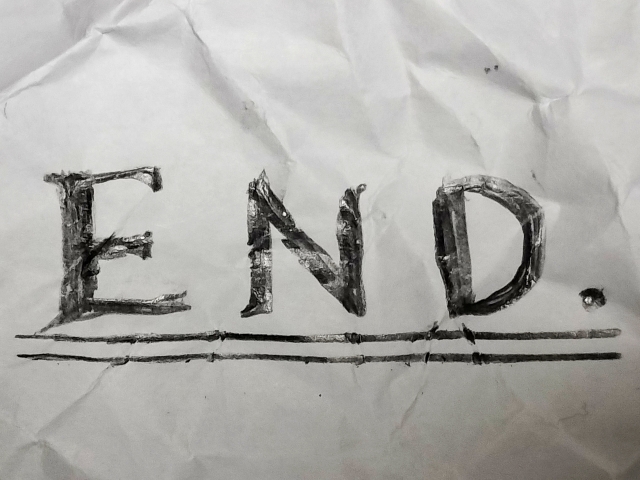採用動画に登場する社員は、単なる「話者」ではありません。応募者が自分を重ねる“未来像の投影対象”です。企業文化の説明や制度紹介だけでは、応募者は働く日のイメージを細部まで描けません。そこで役に立つのが「実在するモデルケース」です。
とくに近年は、入社前の“解像度”を上げたい応募者が増加しています。彼らが知りたいのは 「そこにいる人はどんな価値観で動いているか」「どんな1日を過ごすのか」 といった、書類では分からない部分です。ロールモデルとなる社員が登場するだけで、この情報が整理され、ミスマッチを抑える効果が期待できます。

応募者が重ね合わせる“未来の自分”
応募者は動画を見ながら、無意識に次のようなプロセスで自分を照らし合わせます。
<応募者の内面で起きるプロセス>
1. 自分に近い属性を探す(年齢/役職/仕事スタイル)
2. 価値観の相性を判断
3. 1日の動きを確認
4. 3年後・5年後の姿を想像する
ロールモデル社員は、この内的判断をスムーズにします。
同じ説明でも、人が語ることで“生活感”が入り、数字や制度よりも理解しやすくなるからです。
とくに 若手・中堅・管理職と複数レイヤーを配置する構成は、将来像の段階的イメージにつながります。
動画構成に入れたい3つの軸
ロールモデル社員を登場させる際、以下の3軸で組み立てると、過度にドラマ化せずリアルな描写を保てます。
| ロールモデル社員パートの設計軸 | |
| ① 「仕事内容」軸 | 業務の全体像ではなく、1日の中でどの場面が大切かを中心に。 |
| ② 「判断の根拠」軸 | なぜその行動を選ぶのかを語ってもらう。現場の“考え方”を知れる部分が指示される。 |
| ③ 「働き方の温度感」軸 | 同僚との関わり・息抜きの瞬間など、空気感につながる要素を控えめに盛り込む。 |
この3軸構成は、誇張を避けつつ、応募者の想像に必要な“密度”を確保できます。
ロールモデル社員を選ぶときの注意点
登場させる人物は「優秀な人」ではなく、“その企業らしさを体現する人”を選ぶことが重要です。
営業であれば、成果よりも「企業のスタンダードな働き方を示せるか」が基準になります。
また、動画に慣れていない社員でも問題ありません。むしろ、少し緊張している方がかえって等身大で伝わります。
企業側も「その社員が語られることで誤解が生まれないか」を事前に整理し、業務の特異な場面ではなく“平均値”を拾う編集を心がけましょう。
ミスマッチを減らす採用動画の最終形
ロールモデル社員が出る動画は、企業の人物像の“基準”を提示する効果があります。
求職者は自分との距離を測りやすくなり、誤った期待値で応募するリスクが減ります。
さらに、人の語りには制度説明や代表メッセージでは補いきれない、日常の空気を伝える力があります。
感情的な訴求ではなく、働く風景の温度感を落ち着いたトーンで描くことで、余計な演出を加えずとも理解される動画に仕上がります。
採用動画に“ロールモデル社員”を配置することは、企業と応募者双方にとって大きなメリットがあります。
仕事内容だけでなく、「どう考え、どう動く人が働いているか」を映すことで、入社後のギャップを大幅に減らせます。
過度な演出よりも、日々の判断や温度感を丁寧に拾った構成が、結果的にもっとも伝わる採用動画となります。