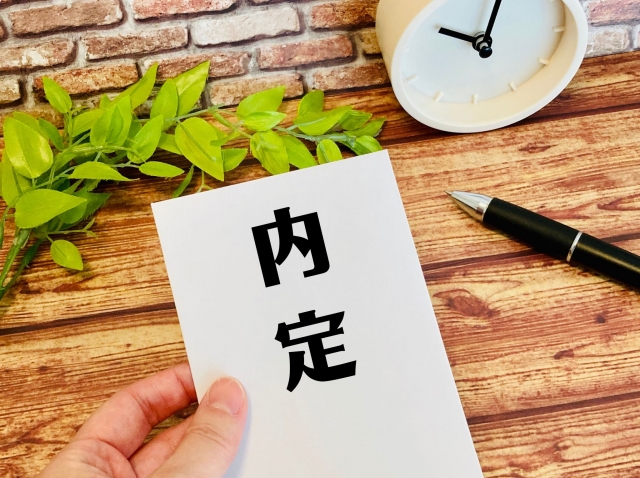採用活動の中で動画の活用が当たり前になりつつあります。とくに会社説明会では「リアルな情報がほしい」という学生のニーズに応える手段として、動画が強力なツールになります。単なる説明ではなく、企業文化や雰囲気を伝えられることが最大の魅力です。
加えて、動画には時間の調整がしやすく、会場の雰囲気をコントロールしやすいという利点もあります。

採用動画の“3本柱”構成とは
会社説明会での動画は、次の3つの要素を軸に構成すると効果的です。
| 動画要素 | 内容 | 狙い |
| 社長挨拶 | 経営理念や将来のビジョン | 組織の方向性や価値観を伝える |
| 現場社員紹介 | 若手・中堅社員の一日や本音 | 働く環境のリアリティを示す |
| 制度・福利厚生紹介 | 研修・評価制度・社内制度 | 入社後の成長や安心感を伝える |
この3本柱を組み合わせることで、「トップの想い」「現場のリアル」「制度面の安心」が揃い、学生が不安なく応募できる環境を整えることができます。
動画の順番と構成のポイント
動画の順番にも工夫が必要です。以下のように流れを設計することで、理解度と印象が大きく変わります。
- 社長挨拶(冒頭)
→企業の理念とミッションを伝え、全体の土台を作る - 現場社員の紹介(中盤)
→日常のリアルな風景やインタビューを通じて“自分ごと化”を促進 - 制度紹介(終盤)
→働き方の安心感・キャリア形成を補強する内容で締める
この順番は、「共感 → 共鳴 → 安心」の心理的導線を作ることができ、記憶にも残りやすくなります。
表現の仕方で印象が変わる
単に説明的な映像を流すだけでは、記憶には残りにくいものです。たとえば、現場社員の紹介では「スマホで撮った日常の様子」を交えるなど、完璧すぎない“素の姿”を織り交ぜることで、親近感が増します。
また、制度紹介では「文字だけで説明」するのではなく、図解や実際の制度活用シーンの映像を取り入れると、視覚的にも納得感が出ます。
よくある失敗と避けるべき落とし穴
ありがちなのは、「キレイにまとめすぎる」こと。編集が整いすぎていると、逆に“作られた感”が出てしまい、リアリティが失われます。
また、動画に詰め込みすぎるのもNG。各パートは2〜3分以内におさめ、テンポよく展開することで集中力を維持できます。あくまで説明会全体の流れの一部として機能させることが重要です。
信頼される採用は、動画の“誠実さ”から始まる
会社説明会で流す動画は、ただの演出ではなく「企業の信頼感を形にする手段」です。
社長の言葉、社員のリアル、制度の説明。この“3本柱”が揃えば、学生が抱える不安に対し、誠実に向き合っている姿勢が伝わります。
豪華な映像よりも、意図と構成が整った動画こそが、採用力を底上げするカギになります。定番の動画構成であっても、一つひとつの表現にこだわることで、採用活動は確実に前進します。