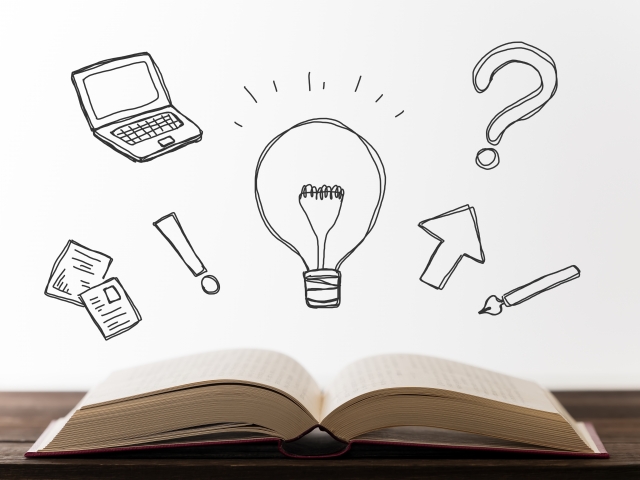ランディングページ(LP)への動画を導入することがあります。
理由の一つは、従来のテキスト中心のLPでは「情報過多」と「読み飛ばし」が起きやすいからです。
特にスマートフォンでの閲覧が主流となった今、ユーザーの滞在時間が短くなり、即時理解が求められる構造に変化しています。
動画は、短時間で商品やサービスの価値を直感的に伝える手段として、非常に相性が良いのです。

動画がもたらす効果とは?文章と画像では届かない領域
テキストや写真では伝えきれない“空気感”や“ニュアンス”は、動画の得意分野です。
以下の表をご覧ください。
| 情報伝達手段 | 訴求力 | 理解スピード | 感情訴求の強さ |
| テキスト | 中 | 遅い | 弱い |
| 画像 | 中 | 中 | 中 |
| 動画 | 高 | 早い | 強い |
特に、サービスの使い方、商品の利用シーン、スタッフの雰囲気などは動画で伝えると圧倒的に効果的です。
加えて、ユーザーは「無音でも意味が分かる動画」であればスクロールを止めやすくなります。
どこに・どんな動画を入れるべきか?配置と構成の考え方
動画を入れる位置は、「ファーストビュー直下」か「CVボタンの直前」が定番です。
前者は第一印象を強化する目的、後者は最後のひと押しに機能します。
また、動画のタイプは目的によって変える必要があります。
- サービス紹介:30〜60秒で概要を伝えるモーショングラフィック
- 商品使用例:リアルな利用風景を映した実写動画
- お客様の声:短めのインタビュー編集
- 会社紹介:採用にも転用できるコーポレート動画
「誰に、何を、どう伝えるか」を動画だけで完結させるのではなく、LPの流れに組み込む意識が重要です。
実際に使われている動画活用例(業種別)
- SaaS系企業:機能説明をアニメーションで見せ、サポート体制も簡潔に伝える
- 住宅・不動産:バーチャル内覧動画で物件の魅力を体験させる
- 人材紹介・派遣:仕事紹介と同時に職場の雰囲気を伝える現場映像
- 飲食・小売業:店舗の雰囲気や調理の様子を見せることで信頼につなげる
いずれも「文章で補足できない体験」を伝えている点が共通しています。
動画導入前に確認すべき注意点とチェックリスト
動画を入れる際に注意すべきポイントは以下の通りです:
- 読み込み速度の低下を防ぐため、軽量化(MP4・WebM)を意識
- 自動再生は音声なしで、ユーザーに操作権を与える構成に
- 動画が「LP全体の流れ」を阻害していないかをチェック
- スマホ表示時の最適化(縦長やレスポンシブ化)
特に「動画が目立ちすぎて他の要素を邪魔してしまう」という失敗も多いため、配置には戦略が必要です。
ランディングページに動画を取り入れることで、訴求力を高めることが可能になります。
特にユーザーの離脱が早い現代において、動画は「瞬時に理解されるためのツール」として有効です。
ただし、ただ入れるだけでは意味がなく、構成との一体感、目的に応じた内容、ページ全体とのバランスが求められます。
軽量化やスマホ最適化などの技術的な配慮も忘れず、成果を上げるLP設計を心がけましょう。