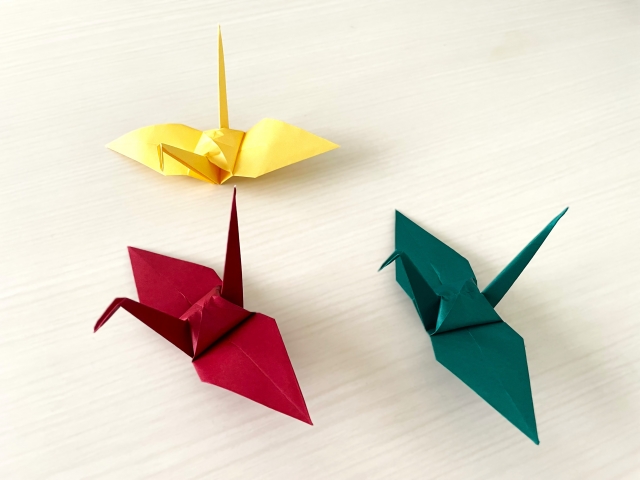採用動画といえば、社員の笑顔やインタビューが中心でした。しかし、「社員紹介では物足りない」という声が若い求職者の間で増えています。
特に、営業・エンジニア・カスタマーサポートなどの職種では、「実際にどんな業務をしているのか」が見えにくいことが不安要素になっているのです。
「優しそうな人」「雰囲気がいい会社」だけでは、入社後の働く姿が想像できない──。そのためには、仕事内容を可視化した“役割紹介動画”がいいでしょう。

「営業職って何するの?」を映像で可視化
採用活動において、「営業って、結局どんな仕事ですか?」という質問は非常に多く見られます。
そこで企業が活用し始めているのが、“業務の流れ”を1分前後の動画で見せる「役割紹介動画」です。
たとえば以下のような構成が効果的です。
| 動画の流れ | 内容例 |
| 出社〜朝礼 | 一日の始まり、チームでの情報共有 |
| 午前の訪問 | クライアントとのやりとり(実写 or 再現) |
| 昼休憩 | オフィス周辺の雰囲気も含めて紹介 |
| 午後の提案 | 提案書の作成やミーティングの様子 |
| 終業・報告 | 日報や退勤までのルーティン |
実際の社員を起用することで、人物の雰囲気も自然に伝わります。
役割紹介動画が持つ3つの効果
- 業務のイメージが明確になる
職種ごとの“働き方のリアル”を見せることで、求職者の理解度が格段に上がります。 - ミスマッチを防ぐ
「入社前に思っていた仕事内容と違う」という早期離職リスクを下げる効果もあります。 - “働く現場”への関心を高める
単なる会社紹介ではなく、「この仕事、やってみたい」と思わせる入口になるのが役割紹介動画の強みです。
注意したいのは“業務紹介”と“作業紹介”の違い
役割紹介動画で注意すべきは、「作業の手順説明」になってしまうことです。
求職者が見たいのは、「どんな目的で・どんな価値を提供する仕事か」という視点です。
ただPCに向かっている様子や書類に目を通している場面だけでは、働く意味が見えてきません。
大切なのは、業務の背景やチームでの連携、判断ポイントなど“仕事の全体像”を伝えることです。
役割紹介動画は“人柄”も伝える
「仕事内容を見せると、人物的な魅力は伝わらないのでは?」という心配もありますが、実は逆です。
役割紹介を丁寧に描いた動画には、言葉以上の人間性がにじみ出ます。
真剣に業務に向き合う表情、丁寧な対応、仲間と話す時の雰囲気──。これらが「この人と一緒に働きたい」と思わせる材料になるのです。
無理に「社員の魅力を見せよう」とするよりも、仕事を通して伝わる“素の姿”のほうが、視聴者には信頼感を与えるのです。
採用動画の主役が「人柄紹介」から「役割紹介」へと変わりつつあります。
求職者が本当に知りたいのは、その職種で自分がどんな風に働けるのか。営業や開発、サポートなど、それぞれの業務を可視化する1分動画は、想像力を補い、ミスマッチを防ぐ有効な手段です。
さらに、役割紹介を通して伝わる“自然な人柄”もまた、企業に対する信頼を醸成します。これからの採用動画は、「何をする仕事か」を軸に据えることで、より深く共感を得るものへと進化しています。